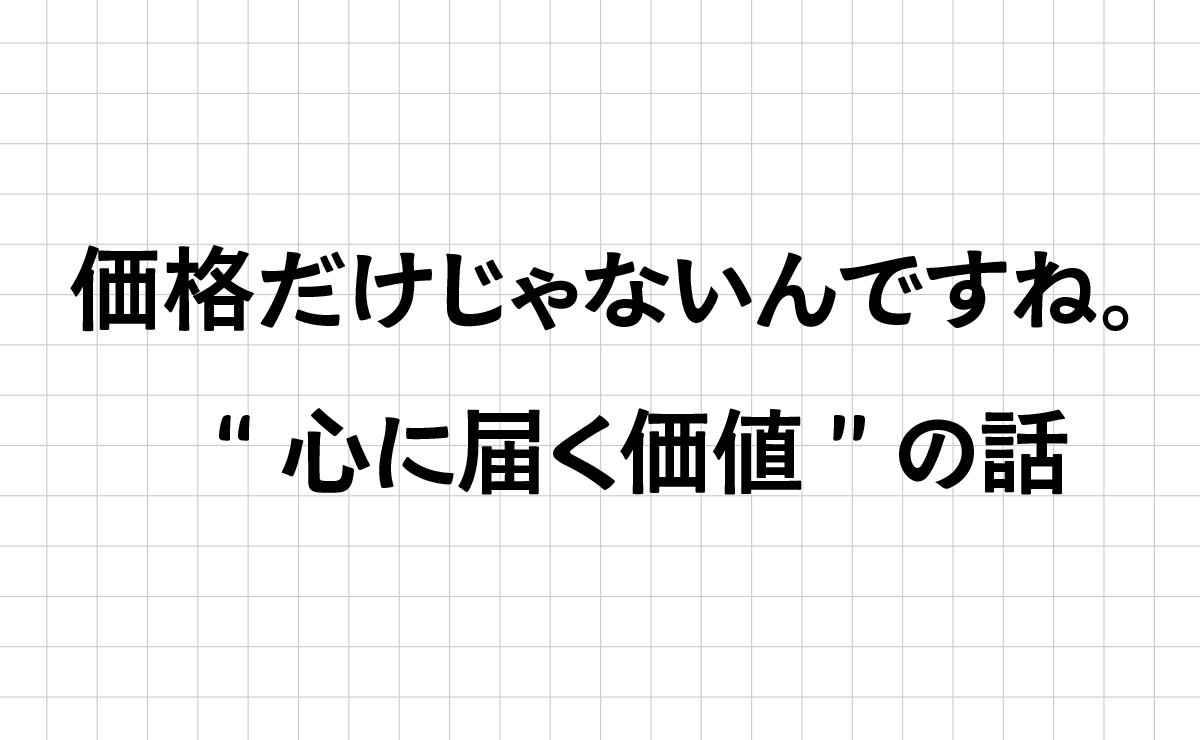毎月1回開催される、マーケティング勉強会に参加しています。
今回のテーマは「顧客満足度と価格戦略」
いまの時代にぴったりの話題だな、と感じました。
きっかけは、値上げラッシュのニュース
というのも、4月だけで4,225品目が値上げ予定というニュースを見て、「これはもうインフレなのでは」と本気で思っていたところです。
うちの店でも一部商品の価格を見直すことにしました。たった数十円のこととはいえ、やっぱり気を使います。
「価格より価値」が選ばれる理由
勉強会で印象に残ったのは、「価格と満足度の関係」についての3つのポイントでした。
1.お客さまは“価格”ではなく“価値”を見ている
たとえば、ファミリーマートの「涙目シール」。消費期限が近づいた商品に貼る値引きシールです。
「助けてください!」という一言がアイキャッチになっていて、思わず手に取ってしまいます。
ただの値引きよりも、「なんとかしなきゃ」という気持ちにさせることで、単に価格が安いだけではなく、“納得感”を生み出しています。
2.満足度が価格の“正当性”を支えている
「この味とボリュームなら、安いわ!」と感じさせるマクドナルド。
少しずつ値上がりしていても、満足度が変わらなければ支持され続けます。“変わらぬおいしさ”が、価格に対する納得感の土台になっているんですね。
3.満足感は、体験からも生まれる
たとえば「餃子の王将」は、地域によって価格が異なることがあります。
でも、その街の空気や店の雰囲気にしっくりくると、不思議と納得できるもの。
「この場所、この感じならこの価格でいい」と思える。それも立派な“情緒的ベネフィット”です。
そして、王将の看板商品・餃子にも小さな工夫が。
実は少しずつ味の改良が加えられていて、「飽きさせないこと」が狙いなんだそうです。
定番メニューであっても、よりおいしく、より満足してもらえるように――そうした努力が、信頼や“この店じゃなきゃ”という気持ちを育てているのだと思います。
小さなお店こそ、コモディティ化に注意
お店そのものが“コモディティ化”してしまうと要注意。
他と差がなくなって、結局は“価格”で比べられてしまうようになり、値下げ競争に巻き込まれてしまうのだそうです。
だからこそ、「ここじゃなきゃ」と思ってもらえることが何より大事。
そのために、毎日の掃除、居心地のよい空間づくり、気取らない接客など、小さな工夫を続けることが必要だとあらためて感じました。
実は“ベネフィット”にも2種類ある
勉強会ではもうひとつ、面白い話がありました。
お客さまが感じる価値(ベネフィット)には、大きく2種類あるというのです。
● 機能的ベネフィット・・・安い、早い、便利、お得、など「スペック的な価値」
● 情緒的ベネフィット・・・嬉しい、楽しい、安心、ちょっと贅沢、気分がいい、など「気持ちに届く価値」
たとえばビールでも――
・毎日の晩酌用なら、安さ重視で箱買い
・仕事帰りの1本には、“ご褒美感”がある
・友人と飲むときには“楽しさ”が
・旅先のホテルなら“非日常の贅沢感”がある
同じビールでも、シーンによって「価値」は変わる。だからこそ、情緒的ベネフィットは軽く見られません。
まとめ:価格より“納得感”を育てよう
これからの時代、必要なのは「値上げしない努力」よりも、「価格に納得してもらう工夫」なのかもしれません。
それは、涙目シールのようなちょっとした仕掛けかもしれないし、マクドナルドや餃子の王将のような積み重ねかもしれません。
私自身も、小さなお店だからこそできることを考えて、お客さまの心に届く価値を、これからも届けていけたらと思っています。