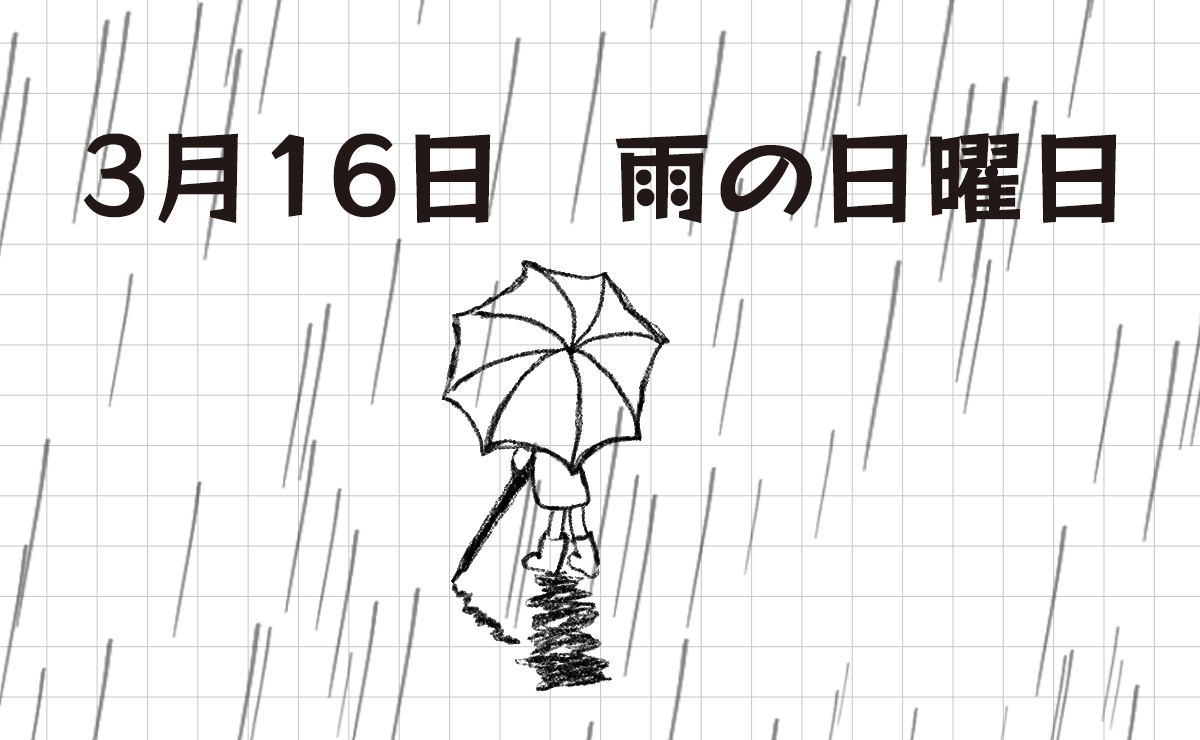ブログの投稿が思うように進まない。
理由はいくつかあって、そもそも書くネタが乏しいというのが一番。
いざ文章を書こうとしたときに、どう書けばいいのかわからなくなる。
いったい何のために書いているのか……
理由はさまざまあります。
好きなことでもあって、そのことについて愛が溢れ過ぎて次から次へと言葉をつむいでしまう。なんていうほどの大好きなことでもあればいいのですが、そんなものも思い浮かばないぼくはどうすればいいのだろう?
そこで最近は文章の書き方に関する本を読み漁っています。
有名どころでは、ライターの古賀史健さん。古賀さんの文章は読みやすく、なぜかページが進みます。
はじめて読んだのは『嫌われる勇気』でした。そして『幸せになる勇気』も、あっという間に読み終わったのを覚えています。
その後、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』『さみしい夜にはペンを持て』『取材・執筆・推敲』と読みました。
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』では、誰に向かって書くのか!という根本の部分を知ることができました。
最近、読んでびっくりしたのは、ナムグン・ヨンフンさんの『みんなが読みたがる文章』です。
文章が書けることは自分を助けるとして、文章を書くにあたってのさまざまな知恵をくれる本でした。
本の読み方、書評の書き方なども学ぶことができてよかったです。
やわらかな文体が親しみを与える、いしかわゆきさんの『書く習慣』は、文章を書き始めたきっかけのエピソードに親近感が湧きます。
肩の力をぬいて自分らしく書くことがいいのだとも感じました。
そして今、髙橋久美子さんの『いい音がする文章』という本と
スティーヴン・キングの『書くことについて』を読んでいます。
ロックバンド「チャットモンチー」のドラマーであり作詞家の髙橋さん。
バンドマンらしく文章にリズムがあり、織り交ぜる方言がいい味を出していて飽きがない。
本のなかで、いい音がする文章として上げている夏目漱石や太宰治、宮沢賢治、芥川龍之介らの作品は、あらためて読むと、なんとも旋律を感じる文章なのです。
いくつもの名作映画の原作を手がけたスティーヴン・キングの『書くことについて』は、古きよきアメリカ映画を観ているような心地よさと思わず吹き出してしまいそうになる体験談に引き込まれてしまいました。
〝書くこと〟は身近なものでありながら、これほど真剣に向き合ったことはありませんでした。
というよりも、それほど本を読んでこなかったのかも。
サラリーマンだったぼくは
人生の大半を自己啓発本やビジネス本を読むことに費やして、技術や知識を増やすことばかり考えていたのかも知れません。
雨降りの日曜日は読書をするにはうってつけの日でした。